『チャイナ・アセアン なぜ日本は「大中華経済圏」を見誤るのか?』の詳細情報
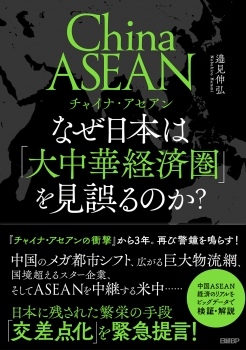
 Amazonで予約する Amazonで予約する
|
タイトル |
チャイナ・アセアン なぜ日本は「大中華経済圏」を見誤るのか? |
| サブタイトル |
|
| 著者 [著者区分] | 邉見 伸弘 [著・文・その他]
|
| 出版社 |
日経BP |
レーベル |
|
本体価格
(予定) |
2700円 |
シリーズ |
|
| ページ数 |
248p
|
Cコード |
0033 |
| 発売予定日 |
2024-09-13 |
ジャンル |
一般/単行本/経済・財政・統計 |
| ISBN |
9784296205479 |
判型 |
A5 |
| 内容紹介 |
米中対立、いわゆる"デカップリング"が喧伝される一方、不動産の暴落など、中国経済の失速がメディアをにぎわせる。そんな状況に日本は安堵していないか? 正しい情勢判断のために、日本は今、何を見るべきなのか──。
リアリズム(現実主義)に立脚する国際情勢分析専門のストラテジストが再び、ペンを執った! モノを見るレンズの「焦点の合わせ方」、そして日本繁栄の手段「アジア太平洋での交差点化」とは!
不振とはいえ中国のGDPは18兆5300億ドルと日本(4兆1100億ドル)の4.5倍。仮に年4~5%成長を続ければ、毎年約100兆円規模の成長を遂げるのだ。
日本が気づかないうちに、浙江省の古都・杭州は人口1200万人のメガ都市となり、東京並みの地下鉄路線が縦横に走る街に大変貌した。ほかにも新1級都市とよばれる数々の都市が、人口減少と言われる中で、常住人口を増やし発展しているのだ。
物流網の発展も目覚ましい。広西チワン族自治区の一寒村だった欽州港は東京港を超える規模に急発展している。この港は、ASEAN(東南アジア諸国連合)と中国を結ぶ玄関口・結節点。ASEANで作られた製品が、欽州から重慶へ、さらに欧州へとつながる物流回廊で運ばれている。
日本は米国に歩調を合わせて脱中国へと動きつつある。中国をめぐる地政学的リスクが声高に唱えられ、改正反スパイ法の影響もあり、人的交流も減っている。だが日本は「大中華経済圏(チャイナ・アセアン)」と距離を置いたままで発展できるのか。巨大市場、製造拠点としてのチャイナ・アセアンを失えば、日本に待っているのは、衰退と高インフレではないのか。
中国は、マクロで見れば不振でも、地域・都市レベルでは大活況を呈しているところが少なくない。そこにどうコミットするか。米中の谷間にあるアセアンはしたたかに存在感を高めつつあるが、日本は冷めた見方をしていないか。
そもそも今後、「米中の関係改善はない」と誰が言い切れるのか。米中関係が復活すれば、待っているのは「ジャパン・パッシング(日本素通り)」どころか、「ジャパン・ナッシング(日本不要)」の世界かもしれない。いや、すでにASEANが米中の結節点になりつつあるのではないか。最悪なのは対立や競争よりも、スルーである。変化の流れに、しっかり噛(か)んでおくことが重要なのだ。
日本はアジア太平洋の産業チェーンの需要な結節点になれる国だ。そうなれるかどうか、今、大きな分岐点に差しかかっている──。
気鋭のストラテジストが改めて日本企業、そして日本が生き残るための「繁栄の道」を徹底解説。現実思考で、情勢をしたたかに見極める必要性を説く。
膨大なデータを取り込んだ中国・アセアン経済のビッグデータも分析。大中華経済圏」のリアルを伝える。
|
| 目次 |
1章 中国悲観論だけでは見えてこない中国の実像
2章 知らぬ間に発展する中国・ASEANの物流回廊
3章 マクロ経済統計から見るチャイナ・アセアンの変化
4章 チャイナ・アセアンで成長を遂げる企業に共通するダイナミズム
5章 大中華経済圏で起こる断片(フラグメント)化とスキャッター化
6章 日本が生き残る道 |