『ライフサイエンスをめぐる倫理的・法的・社会的課題 ~医療と科学の進歩は幸福をもたらすか ~ 』の詳細情報
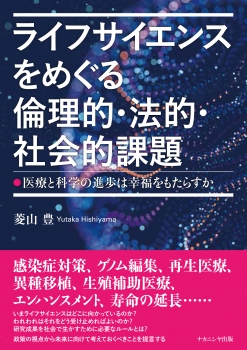
 Amazonで予約する Amazonで予約する
|
タイトル |
ライフサイエンスをめぐる倫理的・法的・社会的課題 |
| サブタイトル |
医療と科学の進歩は幸福をもたらすか |
| 著者 [著者区分] | 菱山 豊 [著・文・その他]
|
| 出版社 |
ナカニシヤ出版 |
レーベル |
|
本体価格
(予定) |
2700円 |
シリーズ |
|
| ページ数 |
216p
|
Cコード |
1036 |
| 発売予定日 |
2025-04-17 |
ジャンル |
教養/単行本/社会 |
| ISBN |
9784779518386 |
判型 |
A5 |
| 内容紹介 |
人類の願いを叶えるためにわれわれがすべきことは!?
いまライフサイエンスはどこに向かっているのか?
どうすれば人類の幸福に結びつけることができるのか?
研究成果を社会で生かすために必要なルールとは?
新型コロナなどの感染症対策、再生医療や異種移植、生殖補助医療、老化研究など、命と健康の課題を克服すべく、ライフサイエンスは日々進展している。それは未来への希望をもたらすとともに、未知の問題もはらむ。
われわれはそれをどのように受け止めればよいのだろうか。どうすれば人類の幸福に結びつけることができるのだろうか。
長年、国の科学政策立案の中枢に携わってきた著者が、現在の到達点をわかりやすく整理し、問題提起と提言を行う。ひと目で各課題の状況がわかるキーワードマップもあり、入門テキストとしても役立つ。
「はじめに」より
新型コロナウイルス感染症のパンデミックの際にも、新しいライフサイエンスの技術が活用され、わずか1年程度でワクチンが開発されて、世界の人々が接種を受けた。では、ライフサイエンスはすばらしいものだから、どんどん進めればよいのかというと、そうでもない。倫理的・法的・社会的課題(ELSI: Ethical,Legal and Social Implications/Issues)をともなうことが多い。ライフサイエンスが進んだ先に何があるのかを考える必要がある。例えば、老化研究によって健康寿命の延伸が実現したときにどのような社会になるのだろうか。生殖医療の進展により、家族制度への影響はどのようなものになるのだろうか。本書では、ライフサイエンスの内容を理解した上で、社会制度についてあらかじめ研究する必要があるということを強調した。
●著者紹介
菱山 豊(ひしやま ゆたか)
1960 年生まれ。東京大学医学部保健学科卒業後、科学技術庁入庁。文部科学省で、生命倫理・安全対策室長、ライフサイエンス課長、科学技術・学術政策局長などを歴任。日本医療研究開発機構(AMED)の設立と経営に参画。文部科学省退官後、徳島大学副学長などを経て、現在、順天堂大学特任教授。博士(医学)。著書に、『生命倫理ハンドブック』(築地書館)、『ライフサイエンス政策の現在』(勁草書房)がある。
|
| 目次 |
はじめに
◆第Ⅰ部 ライフサイエンスの進歩と社会的課題
1 章 ゲノム医療
1.1 ゲノム医療の研究開発の現在
1.1.1 ヒトゲノムとは何か
1.1.2 私たちの試料と情報を集めたバイオバンク
1.1.3 ゲノム医療とは
1.1.4 ゲノム医療のこれから―精密医療へ
1.2 ゲノム科学の進展に対する社会の対応
1.2.1 ヒトを対象とする研究のルールはどうできたか?
1.2.2 海外のヒトゲノムをめぐる倫理的・法的・社会的課題への取り組み
1.2.3 日本のヒトゲノムをめぐる倫理的・法的・社会的課題への取り組み
1.2.4 ゲノム情報は特別な情報なのか?
1.2.5 ヒトゲノムと生物学教育
1.3 ゲノム情報を活用するためのこれからの課題
1.3.1 ルールの複雑化とデータの活用
1.3.2 ゲノム情報と差別
1.3.3 診断ができても治療ができない
【コラム】バイオバンク・ジャパンの20年
2 章 ワクチンの研究開発と感染症への対応―新型コロナウイルスを例として
2.1 ワクチンの研究開発の現在と推進方策
2.1.1 ワクチンの意義と研究開発
2.1.2 メッセンジャーRNA ワクチン
2.2 医薬品開発や医療体制に関する社会の変化と対応
2.2.1 医薬品としての安全性と有効性を担保するルール
2.2.2 疾病構造の変化と医療体制
2.2.3 感染症の対策について
2.3 新型コロナウイルス感染症への対応
2.3.1 専門家の知見は活かされたか
2.3.2 日本におけるワクチン開発の遅れ
2.3.3 ワクチンに対する国民の意識
2.3.4 ワクチンの効果と副反応
2.3.5 ワクチン獲得の国家間格差
◆第Ⅱ部 先端生命科学とルール
3 章 ゲノム編集
3.1 ゲノム編集の概要と期待
3.1.1 ゲノム編集とは何か
3.1.2 ゲノム編集への期待
3.2 ゲノム編集に関わる社会的課題
3.2.1 想定されるさまざまな課題
3.2.2 デザイナー・ベイビーの可能性
3.2.3 社会的課題の検討の方向性
3.3 課題に対する日本での検討
3.3.1 日本の行政府における検討
3.3.2 日本学術会議における検討
3.4 課題に対する海外での検討
3.4.1 英国ナフィールド評議会の検討
3.4.2 米国ナショナル・アカデミーと英国王立協会による検討
3.4.3 ドイツの倫理評議会による検討
3.5 残された課題と今後の検討の方向
3.5.1 誰がどんな問題を検討すべきなのか
3.5.2 暫定的な結論
4 章 再生医療と異種移植
4.1 再生医療の研究開発
4.1.1 iPS 細胞を活用する再生医療
4.1.2 ヒトES 細胞を活用する再生医療
4.2 異種移植の研究開発
4.2.1 米国における異種移植(動物の臓器をヒトに移植)
4.2.2 日本における異種移植の研究
4.3 再生医療に関する社会的課題と対応
4.3.1 細胞を使うことの課題
4.3.2 法律による再生医療の規制
4.4 異種移植に関する社会的課題と対応
4.4.1 米国における異種移植の検討
4.4.2 日本における異種移植に関する調査研究
4.4.3 クローン技術の規制緩和
4.4.4 動物愛護の観点
4.5 知っておきたい背景議論
4.5.1 脳死と臓器移植に関する長い議論
4.5.2 高額な医療への対応
【コラム】2007年の山中先生研究室初訪問
◆第Ⅲ部 新しい生死の概念の登場と私たちの生き方
5 章 生殖補助医療をめぐる課題
5.1 生殖補助医療の研究と期待
5.1.1 生殖補助医療について
5.1.2 出生前診断と着床前診断
5.1.3 発生に関する基礎研究、iPS細胞の活用
5.1.4 人工子宮
5.2 生殖補助医療による社会への影響とその対応
5.2.1 親子や家族の関係はどうなるのか?
5.2.2 新型出生前検査をめぐる問題
5.2.3 着床前診断をめぐる課題
5.2.4 人工子宮が投げかける課題
5.2.5 iPS細胞やES細胞を活用した研究から生じる課題
5.2.6 生殖補助医療は幸せをもたらすのか?
【コラム】日本学術会議への期待
6 章 ブレイン・マシン・インターフェース
6.1 ブレイン・マシン・インターフェース研究の現在
6.1.1 ブレイン・マシン・インターフェースとは
6.1.2 ブレイン・マシン・インターフェースの研究開発
6.2 ブレイン・マシン・インターフェースに関する社会的課題
6.2.1 脳神経倫理学
6.2.2 ブレイン・マシン・インターフェースによる能力向上
6.2.3 マインドリーディング、マインドコントロール
6.2.4 意識のコンピュータへのアップロード
6.2.5 デュアルユース
6.3 課題に対する取り組み状況
6.3.1 OECDの取り組み
6.3.2 ユネスコにおける取り組み
6.3.3 「ムーンショット型研究開発制度」目標1 における取り組み
6.3.4 JST/CRDSのワークショップ
6.3.5 筆者の見解
【コラム】脳科学委員会の創設と「大工の棟梁」
7 章 老化研究と寿命の延長
7.1 老化研究の推進方策と期待
7.1.1 老化研究の推進
7.1.2 産業界の注目
7.1.3 ライフコースを通じた研究の重要性
7.2 老化研究の社会的課題と対応
7.2.1 老化は病気か
7.2.2 老化の制御が可能となった社会のシステム
7.2.3 エイジズム―年齢による差別、高齢者への偏見
8 章 エンハンスメント
8.1 エンハンスメントとは何か
8.1.1 より高い能力をめざすエンハンスメント
8.1.2 先端科学を用いたさまざまなエンハンスメント
8.1.3 老いない身体と精神
8.2 エンハンスメントに関する社会的課題とその対応
8.2.1 能力は与えられたものか?
8.2.2 ゲノムの操作によるエンハンスメントをどう考えるか?
8.2.3 不老長寿はかなえられるべき欲望か?
【コラム】ライフサイエンスのELSIに取り組む学際的拠点の設立
◆第Ⅳ部 新たな科学技術と私たちの社会―政策からの視点
9 章 資源配分の考え方
9.1 ライフサイエンスの研究費をめぐる現状
9.1.1 なぜ研究費が問題となるのか
9.1.2 医療費とライフサイエンスの研究費
9.1.3 宇宙、IT、AIなど他分野研究との競合
9.1.4 製薬産業における研究開発費
9.2 研究費の配分
9.2.1 ライフサイエンス研究費配分の考え方―モダリティ
9.2.2 医学研究費の配分―どの病気の研究を優先するべきか
9.2.3 ライフサイエンス研究費の配分―基礎研究と臨床研究
9.3 資源配分に関する社会としての対応
9.3.1 審議会の効用
9.3.2 国民や患者の幸福につながるか―社会との共創の必要性
【コラム】再生医療の研究費と遺伝子治療の研究費
10 章 研究不正から研究インテグリティへ
10.1 研究不正の変化とそれへの対応
10.1.1 典型的な研究不正
10.1.2 新たなタイプの研究不正―査読に関する不正
10.2 地政学的状況の変化が研究インテグリティに反映
10.2.1 経済安全保障とライフサイエンス
10.2.2 科学技術情報の管理
【コラム】STAP細胞問題の衝撃と悲しみ
11 章 新しい科学技術にどう取り組むか―ライフサイエンスの政策的方向性
11.1 医療政策と産学連携の現状と課題―日米を比較して
11.1.1 米国と日本の医療政策の違い
11.1.2 日本医療研究開発機構(AMED)の設立とその役割
11.1.3 医薬品の産学連携事情
11.2 健康長寿社会と私たちの幸福へのライフサイエンスの寄与
11.2.1 インクルーシブな健康長寿社会に向けて
11.2.2 ライフサイエンスと幸福
11.3 責任ある科学技術・イノベーション政策
11.3.1 責任ある研究とイノベーション
11.3.2 新興科学技術への取り組み
あとがき
注
索引
ライフサイエンス政策関連年表
|
| 著者略歴(菱山 豊) |
| 1960 年生まれ。東京大学医学部保健学科卒業後、科学技術庁入庁。文部科学省で、生命倫理・安全対策室長、ライフサイエンス課長、科学技術・学術政策局長などを歴任。日本医療研究開発機構(AMED)の設立と経営に参画。文部科学省退官後、徳島大学副学長などを経て、現在、順天堂大学特任教授。博士(医学)。著書に、『生命倫理ハンドブック』(築地書館)、『ライフサイエンス政策の現在』(勁草書房)がある。 |