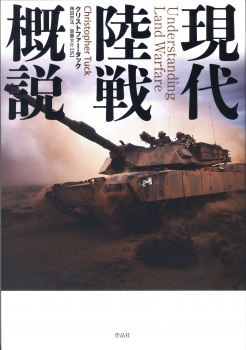
 Amazonで予約する Amazonで予約する
|
タイトル |
現代陸戦概説 |
| サブタイトル |
|
| 著者 [著者区分] | ■クリストファー・タック [著・文・その他]
■梅田 宗法 [翻訳]
■斎藤 大介 [翻訳]
■齋藤 大介 [翻訳]
|
| 出版社 |
作品社 |
レーベル |
|
本体価格
(予定) |
3600円 |
シリーズ |
|
| ページ数 |
|
Cコード |
0031 |
| 発売予定日 |
2025-11-06 |
ジャンル |
一般/単行本/政治-含む国防軍事 |
| ISBN |
9784867931165 |
判型 |
46 |
| 内容紹介 |
世界のプロに読まれている教科書。
一般にもわかるように工夫された最高峰の羅針盤!
本書を読めば、作戦術、ハイブリッド戦、多領域戦、そして中・露が目指す陸戦など、現代の陸戦に関連する語彙、概念、問題および議論を徹底的に学ぶことができる。さらにウクライナ戦争が陥っている今日の状況について明快に理解することができる。
クリストファー・タックの刺激的な本書は、陸戦の優れたタイムリーな入門書であるが、単なる基本書以上のものである。(ゲイリー・シェフィールド、英国ウォルバーハンプトン大学名誉教授)
本書は、よく書かれ、よく研究され、陸戦を幅広く探求している。素晴らしい。常に明晰で、魅力的で、非常に読みやすい文体で、陸上戦のあらゆる側面を探求し、解明している。(アンドリュー・シャープ少将[CBE勲章受賞者])
【内容目次】
現代陸戦概説
第二版への序文
序章
第Ⅰ部 陸戦の発展
第一章 理論上の陸戦
第二章 現代陸戦の発展
第三章 現代戦術
第四章 現代の作戦術と戦争の作戦レベル
第五章 陸戦‐文脈と差異
第Ⅱ部 勝利とは何か
第六章 対反乱作戦
第七章 平和・安定化作戦
第八章 ハイブリッド戦
第Ⅲ部 将 来
第九章 将来の陸戦
第十章 範例的[パラダイム]陸軍
第十一章 ロシアと中国
結論
訳者後書き
解説
用語集/参考文献/索引
|
| 目次 |
現代陸戦概説
第二版への序文
序章
(なぜ地上なのか/なぜ、武力戦なのか/戦争の諸階層とは何か/戦略レベル/作戦レベル/戦術レベル/現代の陸戦とは何か/本書の概要/第Ⅰ部 陸戦の発展/第Ⅱ部 勝利とは何か/第Ⅲ部 将来/本書の主要テーマは何か)
第Ⅰ部 陸戦の発展
第一章 理論上の陸戦
陸上領域[ランドドメイン]の特性とは(政治的重要性/多様性/不透明性/抗堪性/可変性)/陸上戦力の特性とは(諸特性/長所と短所)/ランド・パワーの依存的性質(戦略と政策/統合戦と多領域戦[マルチドメイン・ウォーフェア]/統合戦の課題/心理面)/陸戦‐ 重要な原則と概念(現代陸戦の力学/戦争の規模/火力/運動性/兵站/指揮・統制/戦争の原則/火力と機動/機動と消耗/破壊と混乱/集権と分権/調和と主動/単独兵科と諸兵科連合/集中と分散/攻撃と防御)/小括/要点/問い
第二章 現代陸戦の発展
革命なのか進化なのか(軍事革命と陸戦/進化に関する議論/軍事革命という概念への批判/軍事革命における継続の重要性)/軍事変化の原動力(軍事革命の多様性/軍事技術革命/軍事における革命(RMA)/軍事社会革命/複合的な視点)/小括/要点/問い
第三章 現代戦術
現代戦術の基礎(現代戦術の原則)/一九〇〇〜一九一四年の陸戦(火力対銃剣/議論の解決/一九一四年の軍事ドクトリン)/初期の適応/現代戦術(複合的な進化/ドイツ軍の浸透戦術/分権/擾乱/準備)/現代の戦術防御/現代戦術/小括/要点/問い
第四章 現代の作戦術と戦争の作戦レベル
作戦術とは(作戦術の定義/作戦術に共通する主題/重要な変数)/作戦術の展開(歴史的起源/一九一八年と戦術の欠点/戦間期と作戦術/イギリス、フランスおよびアメリカ/ソビエトによる作戦術の体系化/ドイツの電撃戦/電撃戦の臨機応変の特性/第二次世界大戦/作戦術の限界/作戦術の継続的なつながり/消耗の重要性)/戦争の作戦レベル(冷戦/アメリカの作戦レベルのドクトリン/発展の広がり/エアランド・
バトル)/批判と論争(作戦術に関する論争/作戦レベルについての論争/将来に向けて)/小括/要点/問い
第五章 陸戦‐文脈と差異
陸軍の適応と革新を形作るものは何か(軍事競争と軍事変化の源/互換性と適応/陸軍における変化の概念化)/文脈と差異(現代システムの多様な適用/差異と戦争の特質の関係性/非互換性と現代システム陸戦/非西側の戦争と軍事的有効性)/小括/要点/問い
第Ⅱ部 勝利とは何か
第六章 対反乱作戦
反乱とは何か(反乱の特徴/反乱のモデル/反乱の歴史的発展/反乱の理論の出現/毛沢東主義者の思考/フォコイズム)/対反乱とは何か(帝国治安維持とは何か/ユベール・リョテとジョセフ・ガリエニ/チャールズ・コールウェル/アラビアのロレンス/チャールズ・グウィン/アメリカ海兵隊/帝国治安維持アプローチの限界とは何か/対反乱の黄金期/古典的対反乱とは何であったのか/ダヴィッド・ガルーラ/ロバート・トンプソン卿/フランク・キットソン卿/古典的な対反乱の原則/現代の対反乱ドクトリン)/対反乱戦の課題(対反乱活動における成功とは何か/ COINの原則を適用する上での問題/現代の反乱をめぐる議論/新古典派/グローバル反乱派/安全保障政策派の視点/対反乱酷評派)/小括/要点/問い
第七章 平和・安定化作戦
平和活動[ピースオペレーション](平和活動の起源とは何か/冷戦間の平和活動/伝統的平和維持の原則/平和維持活動から平和活動へ/変化の源泉/量的および質的発展/ドクトリン上の進化/新たなアプローチ/平和活動と平和支援活動/「多次元平和維持」/平和活動の要則)/安定化作戦(安定化作戦の出現/国連による安定化/国連以外による安定化)/平和・安定化作戦の課題(活動状況/介入の特性/理論対実践/MINUSMA‐平和活動の事例研究/平和活動の効用/非国連安定化の有用性)/小括/要点/問い
第八章 ハイブリッド戦
ハイブリッド戦とは何か(ハイブリッド戦の概念の発展/ロシアのハイブリッド戦争/ハイブリッド戦の主な特徴/ゲラシモフ・ドクトリン)/より広範な課題としてのハイブリッド戦(中国/イランのハイブリッド戦争/ハイブリッド戦への対応)/ハイブリッド戦の議論(定義の不正確さ/本当に新しいのか/捏造された概念/誇張された効果)/小括/要点/問い
第Ⅲ部 将 来
第九章 将来の陸戦
ネット中心戦(一九九〇〜一九九一年の湾岸戦争/軍事における革命/いかなる種類の革命か/コソボとアフガニスタン/バランスの回復/ネットワーク中心のRMA/ネットワーク・セントリック・ウォーフェア/ネット中心のモデル)/将来の武力戦をめぐる議論(ネットワーク中心のパラダイムの弱点/革命ではなく進化/証拠の欠如/過度の科学技術偏重/自滅的な性質/予測の危険性/将来を予測する/他に有効なパラダイムはあるのか/パラダイムは役に立つのか/陸戦の複数の特性/軍の柔軟性と適応/柔軟性の利点/柔軟性への挑戦)/小括/要点/問い
第十章 範例的[パラダイム]陸軍
トランスフォーメーションという概念の出現/トランスフォーメーション(トランスフォーメーションとは何であったのか/陸軍トランスフォーメーションの次元/トランスフォーメーションの議論/アフガニスタンとイラクという証拠/不確実な未来)/変化の力学(加速/均等化/情報化/ハイブリッド化/ 領域[ドメイン]の拡大と縮小/変化が意味するもの/透明性/致死性/速度/拡張/融合/新たな機会)/多領域作戦(多領域作戦の原点/多領域作戦の主要原則/ハイブリッド化/主要な要則/陸戦における革命か)/MDOの効果は(科学技術は実現するか/MDOは野心的すぎるのか/ MDOは脆弱すぎるのか/ MDOは実戦と無関係なのか)/小括/要点/問い
第十一章 ロシアと中国
ロシア(ソビエト後のロシアの危機/変化の力学/防衛計画「改革」/改革の主要テーマ/職業専門化/編制改革/指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視および偵察(C4ISR)/新しい科学技術/アップグレード/非対称アプローチ/ウクライナとシリアでの活動/シリアからの教訓/ロシアの軍事近代化はどの程度効果があったのか)/中国(過去の動き/変化の力学/情報化戦/情報化の特徴/情報の重要性/規模と編制/一体化/宇宙とサイバー/兵器技術/専門職業化/運動性/「知能化戦」/人民解放軍改革の効果)/ヒズボラ/小括/要点/問い
結論
訳者後書き
解説
用語集
参考文献
索引 |
| 著者略歴(クリストファー・タック) |
| 英国国防大学でもあるキングス・カレッジ・ロンドンで戦略研究学部の准教授を務めている。それ以前は、サンドハースト王立陸軍士官学校の上級講師を務めていた。 |
| 著者略歴(梅田 宗法) |
| 現在、北部方面隊法務官。1996年、明治大学法学部卒業後、陸上自衛隊に入隊。以降、第9戦車大隊小隊長、幹部候補生学校教官、第1戦車大隊中隊長、陸上幕僚監部幕僚(教育訓練計画等担当)、研究本部研究員、西部方面総監部訓練課長、統合幕僚学校教官、第72戦車連隊長兼ねて北恵庭駐屯地司令。 |
| 著者略歴(斎藤 大介) |
現在、陸上自衛隊教育訓練研究本部教育戦史教育室(戦史教官)勤務。1995年3月防衛大学校卒業。2006年4月第10次イラク復興支援群勤務。2010年3月防衛大学校総合安全保障研究科前期課程卒業。2010年3月防衛大学校防衛学教育学群戦略教育室准教授2016年 3月防衛
大学校総合安全保障研究科後期課程卒業。2016年8月博士号(安全保障学)取得。 |
| 著者略歴(齋藤 大介) |
現在、陸上自衛隊教育訓練研究本部教育戦史教育室(戦史教官)勤務。1995年3月防衛大学校卒業。2006年4月第10次イラク復興支援群勤務。2010年3月防衛大学校総合安全保障研究科前期課程卒業。2010年3月防衛大学校防衛学教育学群戦略教育室准教授2016年 3月防衛
大学校総合安全保障研究科後期課程卒業。2016年8月博士号(安全保障学)取得。 |